こんにちは、赤塚です。
先日、子どもと一緒に読むための本を借りようと、図書館に行ってきました。
とにかく家でも外でも、アンパンマンが大好きすぎるので、
その関連のもので遊ぶことが多いんですが、もっといろんなものに触れてほしいな、とも思い、
僕の独断で、写真が多く見やすいものをいくつか借りてきました。
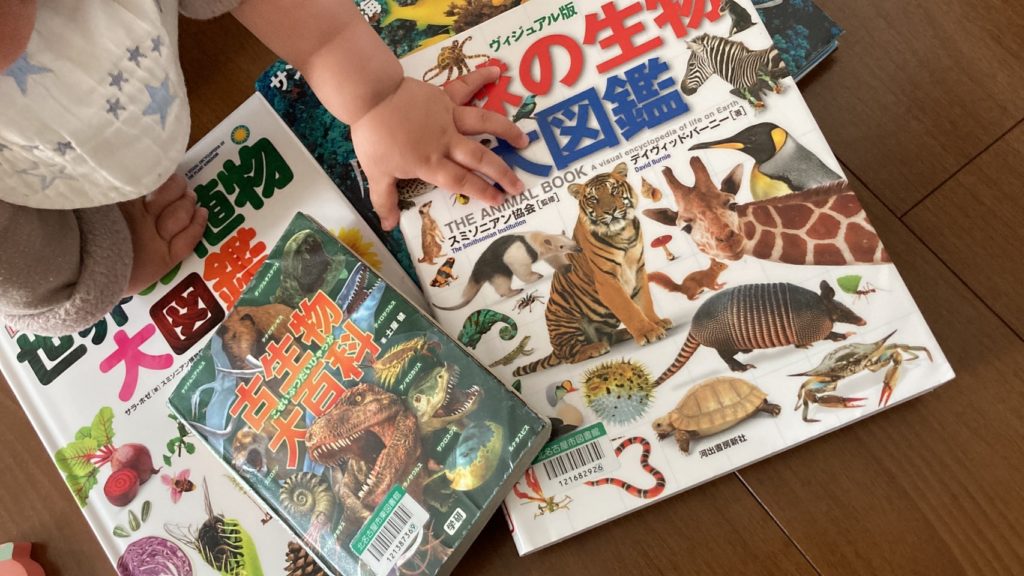
植物図鑑・動物図鑑・サンゴ・古生物大百科、を借りてきて、
普段は動物のおもちゃで遊ぶことも多いので、そこにハマるかな?なんて思っていたんですが、
今回、一番ハマったのはなぜか『恐竜』で。笑
さらに驚いたのは、表紙の恐竜の絵を見て、「がおー!(まだ1歳半で喃語ではありますが)」と声を出し、
僕も妻もびっくり。
今まで恐竜なんて見せたことなかったんですが、どこで覚えたのか、はたまた、たまたま合っていただけなのか。笑
そんな、子どもがハマった「古生物大百科」の本を読んでいると、
中学の理科科目に通ずる内容がちょこちょこ入っていて。
化石や、時代に関して、言葉(古生代・中生代・新生代など)もそのまま載っており、
もし小学生時代にこの本を手に取っていたら、中学時にこれらの言葉に出会うのも二度目で。
過去、興味もあり、聞いたこともある単語をもう一度知る・覚える生徒と、
全く出会ったこともなく、興味もなかった単語を知る・覚える生徒では、
その学習スピードは大きな差が出てくると思います。
これは何も、読書だけでなく、ゲームでも、旅行でも、TVでも、Youtubeでも、はたまた家族の会話でも同じだと思っていて、
新しいものに触れる機会が、子どもの脳の発達には良いそうです。
とはいえ、「今からそんなことやっても、、」と思っていらっしゃるご家庭の方も多いかもしれません。
今回お伝えしたいのは、「本をたくさん読んで、いろんな経験をしろ!」というよりも、
身の回りにある、小さなことにいかに興味を持てるか。
それがモノなのか、人なのか、情報なのか、お金なのかは人それぞれですが、
興味・関心、そして疑問を持てるかどうかが、
日々取り組んでいる勉強にも関係してくるんじゃないかなぁ、と僕は思っています。
忙しいときでも、子どもの「なんで?なんで!?」には、手を止めて、
一緒に考えたり、話したり、調べる時間を大切にできる人でありたいです♪


